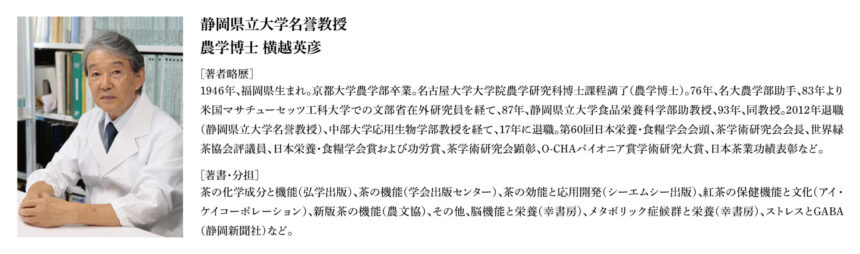〈食と美と健康〉咀嚼と健康な歯:健全な脳機能の維持

脳の発育に対しては栄養も関与しますが、栄養が同じであれば、よく噛んでも噛まなくても同じでしょうか。最近の食べ物は軟らかく、子供達は硬い食べ物を好まなくなっています。そこで次の実験を紹介します。同じ親から生まれた仔ネズミを離乳直後2群に分け、片方には硬い固形の餌を与え、もう一方のネズミにはその餌の粉末を与え、5週間飼育しました。その後、迷路学習や条件回避学習試験を行い頭の良さ「学習能」を調べました。迷路実験のエラー点数をそれぞれ10匹のネズミの平均値で比較すると、固形食群で136、粉末食群で216となり、粉末食を食べたネズミの方がミスの多いことが分かりました。また電気ショックを与える条件回避学習試験でも、固形食ネズミの方が粉末食ネズミより回避率が高く、学習効果の優れていることが分かりました。良く咀嚼すると脳細胞の代謝が活発になり、血液循環も良くなり大脳の温度が上昇したことが一因とも考えられました。

人での咀嚼と知能の発育との関係については、幼稚園での調査があります。噛む力、咀嚼能力と知能テストとに相関はありませんでした。しかし、4~6歳児の噛む力と幾何学図形テスト(三角形などの手本を見て、それと同じ図形を描かせるテスト)との間には相関が認められました。噛むことと脳の働きとは関係がありそうです。精神病の患者さんや少年院の若者達は一般に早食いであるといわれます。過食症になる場合もあります。お茶でも飲みながら、落ち着いてゆっくりと食事をすることが、心の安らぎを生むのに大切です。良く噛んで食べると少量の食事で満足し、食べ過ぎないので肥満にならない利点もあります。よく噛むことは虫歯の予防だけでなく、歯の健康、脳機能を含めた心の健康にも大切であり、いつまでも丈夫な歯を持ち続けたいものです。
静岡県立大学名誉教授
農学博士 横越英彦 著
-